「誰でもできる仕事」と言われる職場でよく感じる疑問について考えてみたいと思います。
「この仕事、別に誰がやっても同じだよな…」
「なんでこの人、こんなに態度が悪いんだろう…」
そんな風に感じたことはありませんか?
実際、私も過去にいくつかの職場で、「これは…まともな人が少ない」と感じる現場に出会ったことがあります。そしてその共通点は、“仕事内容が極端に単純”で“誰でもできるとされている仕事”だったことです。
では、なぜそういう職場には「まともな人」が定着しにくいのでしょうか?
1. 単純作業の職場は、優秀な人材が長く居つかない
まず最初に言えるのは、単純な仕事はスキルや経験を積んでも評価されにくいため、成長意欲のある人はすぐに辞めてしまうということです。
「やれば誰でもできる」ということは、「やっても評価されにくい」ということでもあります。
優秀な人、責任感がある人ほど「ここにいても将来が見えない」と感じ、転職やキャリアアップを目指して去っていきます。
結果として、「やる気がない人」や「他で通用しなかった人」が残りやすくなってしまうのです。
2. 社内に“人間関係でしかマウントを取れない人”が増える
仕事の中身で差がつきにくい職場ほど、他人をいびったり、悪口で連帯感を作ったりする文化が生まれやすい傾向があります。
特に単純作業の現場では、仕事の成果ではなく「誰が誰に気に入られているか」「誰が嫌われているか」が重要になってしまうケースがあります。
そうなると、人間関係がギスギスし、「まともに働きたいだけの人」が居づらくなるという悪循環が生まれます。
3. 労働環境の質が、職場の民度を左右する
「誰でもできる仕事」は、往々にして低賃金・長時間労働・不安定な雇用形態といった悪条件が重なりがちです。
すると、ストレスが溜まり、心の余裕がなくなり、人への当たりもきつくなります。
「まともだった人」も、徐々に壊れてしまうことすらあります。
4. 「誰でもできる仕事」だからこそ、管理者の質が重要
誤解のないように言っておくと、「単純な仕事自体が悪い」という話ではありません。
むしろ、そういった仕事を支えている人たちがいるからこそ社会は成り立っています。
問題なのは、「誰でもできる」と思われているがゆえに、現場のマネジメントが軽視されがちなことです。
管理者がしっかりしていれば、どんな職場でも風通しはよくなります。
まとめ:環境が人を作る。そして壊す
結局のところ、「誰でもできる仕事内容」そのものが問題なのではなく、
その環境において「人が育たない」「評価されない」「人間関係が悪化しやすい」ことが、まともな人が少なくなる原因です。
「人が定着しない」
「注意しても改善されない」
そんな職場に共通するのは、“仕事の中身よりも、環境の悪さ”なのかもしれません。
もし今、あなたがそういう職場で悩んでいるなら、
「自分が悪いんじゃない」
という視点を持ってみてください。
そして、心が壊れてしまう前に、距離を取ることも一つの選択肢です。

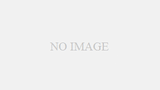

コメント